 |
|
 |
|
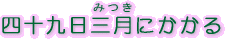 |
|
|
「四十九日が三月にまたがったら、いかんのでしょう?」という質問をよく受けます。これは、「始終苦が身につく」という語呂合わせからきたもので全くの迷信だといえます。ご法事は、なるべく本来の日時に近い日を選んで行うのが良いでしょう。ほかにも、「四十九日の間、死んだ人は成仏できずにさまようのでしょう?」という質問があります。浄土真宗では、人は臨終と同時に仏(諸仏)になると考えるので、中陰期間は、故人に対する追慕、故人を縁として「生と死」について考え、謹慎し求法の生活をする期間であるとします。 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
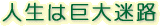 |
|
|
人生は巨大迷路です。スタートしたらゴールまで迷いを離れることができません。ただ、初めから迷いの中にいるせいか、迷いの中にいる自覚すらないのも当然です。
「生」の反対は「死」だと思っていますが、仏教では「生死一如」といって、別々のものではなく、一つのものと見ていきます。生まれたらそこに死が兼ね具っているというわけです。
巨大迷路の中にいることを知らされれば、ゴールは「迷いからの解放」と喜べますが、迷いを迷いと知らない人は、ゴールを「死」と呼び、おびえなければなりません。迷いを脱出する方法は、仏の力(他力)意外にありません。 |
|
 |
|
 |
|