 |
| 村上信哉 |
|
ののさまは
口ではなんにも言わないが
あなたのしたこと知っている
知っている |
|
これは娘の保育園で「ののさまの時間」の一番最初に歌う歌の歌詞です。今年から長女が保育園に入園しました。始めの数日、元気に登園した娘は風邪をひき、三日間お休みをしました。ところがそれを境に登園拒否が始まります。宥め賺してして連れては行くものの、毎朝保育園には行かないと泣きわめきます。この原因はどうも給食ぎらいにあるようでした。
娘の保育園と書きましたが、私は縁あって、四年前にこの保育園の副園長を仰せつかり、現在は園長という立場にあります。この保育園は、浄土真宗以外に日蓮宗・浄土宗・曹洞宗の寺院が五ヶ寺で経営しており、園長は三年の任期で交代することになっています。ですから、たまたま私が園長の時に長女の入園が重なったわけです。
昼頃になると、「泣かずに食べているだろうか、先生を困らせていないだろうか」と、日頃はめったに通らないそのクラスの前を用もないのにうろうろしている親の姿があることに気づかされます。これこそ、目連尊者の母のごとく、餓鬼道まっしぐらの愛欲の世界そのものです。
現在212名の園児がいますが、娘が入園するまでは、園児達をただ一様に眺めていたような気がします。つまり、お昼ごはんをたくさん食べる子もいれば、そうでない子もいる、喜んで食べる子もいれば、嫌がる子もいる、と。しかし、我が子のことになると違います。どうしてだろうかと原因を探りながら、どうすれば保育園を好きになるだろうかと、導く手だてを考えるようになります。「五劫これを思惟して摂受す」(正信偈)とありますように、阿弥陀様という方も、底下の凡愚をお浄土参りの機としあげるため、永きにわたるご思案があったに違いありません。 |
|
いいこと聞いた
良いこと聞いた
りすけがほとけに成ることきいた
きいて、きいて、聞きぬきみれば
りすけがおちる機が知れた
おちるりすけにゃ違いはないが
ほとけが邪魔しておちられぬ |
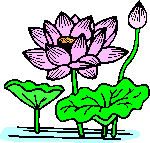 |
|
昨年末に、ある御住職様から伺った、りすけ同行という方のありがたいご法義の詩です。おちる私を、どこまでもおとさせない阿弥陀様のご催促をこの身にいただくことであります。
さて、私の生まれ育った寺の門徒に、武丸正助というありがたいお同行がいました。かれこれ三百年ほど前の人ですが、あまりの親孝行ゆえ、黒田藩の殿様からも何度も表彰されたほどの人物で、「妙好人伝」(安政五年・正聚房僧純集録)や多くの書物に登場します。正助さんはごく自然にお念仏と出遇われたようですが、そのご信心をいただく姿を |
|
もろ人の親につかうる
手鏡となるてふ影は
千世もくもらじ |
|
と、殿様が賞賛するほどでした。
正助さんは正直者で通っていましたが、それを試そうとする者があり、人影のない道に三百文の入った財布を置き、お寺参りから帰ってくる正助さんを隠れて待ちました。やがて通りかかった正助さんは、しばらくそばに立っていましたが、そのうちに座り込んでしまいました。いつまでたっても通行人もなく、正助さんが動く気配もないために、しびれを切らした一人が出てきて訳を尋ねると、落とし主が困っているだろうから、あらわれるまでここで番をしている、とのこと。試した方がその行いを恥じた、という話を、幼い頃よりよく祖父に聞いたものでした。冒頭の「ののさまの歌」にも通じる世界をいただくことであります。
たくさんな逸話が残る中でも、間違いなく他力の信心をいわんとする話を紹介いたしましょう。
ある日のこと、ぐずついた天気の中、正助さんが出かけようとすると、父親が「今日は雨になるだろうから、下駄で行くとよい」と言います。下駄で出ようとすると、母親が「今日は雨は降らないだろうから草履で行くとよい」と言います。そこで、正助さんは片足に草履、片足に下駄を履いて出かけました。
この話を子供の頃に聞いた時には、奇特な方もおられるものだと思うくらいでしたが、今となって私が、片足に雪駄、片足に革靴を履いて出かけられるかというと、なかなかできるものではありません。それはさておき、正助さんのこの行いには、まったく「わたくし」が入る余地がありません。つまり、「わたくし」が入っていれば、自らの判断でどちらにするかを決めていたということです。まさに、聞いたまま、仰せのまま、という世界が窺われます。
南無阿弥陀仏のみ教えを聞いて、信じるか否か、素晴らしい教えかそうでないかなどを私が決めるのであれば、それは仏説よりも私が正しいことになります。聞いて、なおかつ、自分の判断が加われば、それは聞いたことにはならず聞き誤ったことであり、受けとり損なったということになりましょう。これは、「わたくし」が先行する第二十願の立場ということになります。第十八願の他力信心は、「わたくし」が加わる余地が無く、「わたくし」が求めるに先行して、すでに与えられていることであります。現代人は「浄土は本当にあるのでしょうか」などという質問を投げかけますが、他力信心をいただくとき、そうした質問の答えは、その質問に先行してすでに用意されているといえましょう。 |