| 慶長 8年 | (1603) | 小倉城下町縄張りにて浄蓮寺本堂建立、浄喜寺二世(村上壱岐守)良祐を開基とする。 |
| 慶長10年 | (1608) | 本願寺より亀谷山浄蓮寺の寺号下る。 |
| 正保 4年 | (1647) | 本願寺良如上人より三朝高僧真影上宮大師親鸞聖人、准如上人真影下さる。 |
| 延宝 4年 | (1676) | 丙辰、永照寺より、浄蓮寺八世が幼少につき、年頭の御挨拶ができず、御目見寺院のつとめに対する御詫び覚書を小倉藩寺社奉行に提出した。 |
| 元禄 6年 | (1693) | 浄蓮寺九世浄圓幼少につき、永照寺より寺社奉行に宛てた口上之覚書あり、時に浄圓十歳。 |
| 正徳年間 | (1711〜) | 小笠原藩御目見格式寺院を次の通りに定む。 京都郡稗田・大吉寺 高来・天聖寺 新津・清林寺 仲津郡今井・浄喜寺 今井・善徳寺 大橋・浄蓮寺 大橋・禅興寺 国分・国分寺 上坂・観音寺 徳政・明善寺 綾野・普門寺 柳井田・福正院 今井・西福寺 (以上京都郡三ケ寺 仲津郡十ケ寺) |
| 享保 3年 | (1718) | 浄蓮寺十世梅谷代 本堂再建。六間、七間瓦葺、春日御作の本尊阿弥陀如来(木造)御長二尺六寸を安置。 |
| 延享 3年 | (1746) | 浄蓮寺末庵、正山庵建立。庵主光慶を開基、境内96坪。 |
| 宝暦 8年 | (1749) | 浄蓮寺鐘堂建立。(八尺四方瓦葺) |
| 宝暦11年 | (1753) | 浄蓮寺山門建立。(一間半、二間瓦葺) |
| 明和 2年 | (1765) | 浄蓮寺末庵、末江村道場を建立、大悟を開基とする。 |
| 安永 4年 | (1775) | 本願寺法如上人より湛如上人畫像下賜、願主十世梅谷。 |
| 天明 5年 | (1785) | 浄蓮寺末庵喜楽庵を建立、庵主義道開基、境内45坪。 |
| 寛政11年 | (1799) | 浄蓮寺平等庵建立、宝雲を開基とす。境内40坪。 |
| 文化 2年 | (1805) | 本願寺本如上人より蓮如上人畫像下賜、願主十二世雪厳。 |
| 文政 4年 | (1821) | 本願寺本如上人より文如上人畫像下賜、願主十三世恵明。 |
| 文政11年 | (1828) | 大橋大火により、浄蓮寺・禅興寺ともに類焼。 |
| 天保 3年 | (1832) | 本願寺広如上人より本如上人畫像下賜、願主十三世恵明。 |
| 天保13年 | (1842) | 大橋村大火、当山焼失。 |
| 天保14年 | (1843) | 再建、第十三世恵明代。 |
| 明治 3年 | (1870) | 豊津藩より民部省に報告する寺院取調書に下記記載あり、 豊津藩管轄所 寺院明細帳 山城国 京都府六条 本山西本願寺直末 豊前国仲津郡 大橋村 浄蓮寺 住職 良雲 一、境内四百坪 一、滅罪檀家 五百八十軒 |
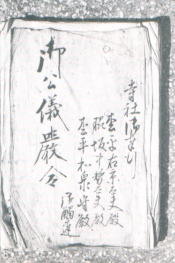 |
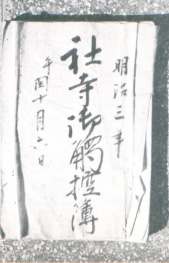 |
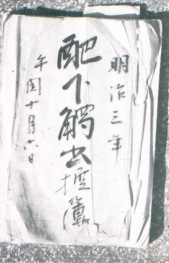 |